canonical(カノニカル)タグとは?【使い方と設定方法を解説】

「canonicalタグってなに?」
「canonicalタグってどういうときに使うの?」
こういった悩みにお答えします。
監修者:しょうた
この記事を書く私は、Webマーケティング会社のSEOコンサルタントとしてさまざまな企業サイトを担当。現在は美容クリニックの専属Webマーケターとして働いています。SEOで上位表示を目指すサイト設計やキーワード選定、コラムの執筆・内部対策などを担当しています。
「canonical(カノニカル)ってなに?」 という悩みを抱えていませんか?
私もSEO会社に入社するまでは、canonicalタグの存在すら知りませんでした。
ソースコードが苦手な人は嫌悪感を覚えるかもしれませんね。
canonicalタグとは、簡単にいうとインデックス最適化の施策です。
検索エンジンにとって読み取りやすいサイトにすることができます。
もしcanonicalタグを使わなければ、SEOのマイナス評価を受けるかもしれません。
しかし、この記事を読めばcanonicalタグの使い方から設置方法までわかります。
この記事を読み終えたときには、canonicalタグの知識が身に付いて、Googleから好かれるサイトが作れるでしょう。
canonical(カノニカル)タグとは?

canonicalタグとは、ページ(記事)内容が類似・重複している場合、正規のURLがどのページ(記事)なのかを検索エンジン(Google)に伝えるタグです。
一つのサイト内に類似・重複するページが複数あるとき、検索エンジンは最も最適と判断したページを検索結果の上位に表示します。
そのため、あなたが表示させたいと思っているページが表示されなかったり、表示させたくないページが表示したりすることがあります。
このときにcanonicalタグを設定すると、どのページを優先的に表示させるのかを検索エンジンに伝えることができるのです。
後ほど詳しく解説しますが、簡単に設定方法を紹介します。
Aページに類似・重複したBページがあったとします。
Bページのheadタグ内に「link rel=“canonical”href=“URL”/」を記入することで、Aページを正規のURLと検索エンジンに伝えることができます。
正規のURLとは?【URLの正規化】
正規のURLのことをURLの正規化といいます。
URLの正規化とは、URLが異なり内容が類似・重複しているページが複数あるとき、検索エンジンから評価を集めたいURLを統一することです。
検索エンジンはURLでページを識別しているため、同じ内容のページでもURLが違っていれば別ページとして認識します。
類似・重複ページがたくさん存在している場合、下記のリスクがあります。
- SEO評価が分散する
- ペナルティの対象になる
- 被リンク数が正しく評価されない
ただ、canonicalタグでURLの正規化をすれば、正規のURL以外の類似・重複ページはインデックスされません。
canonicalタグを設定するのは、SEOでも重要な施策になります。
301リダイレクトの違いは?
301リダイレクト(恒久的な転送)は、強制的にページを転送してURLの正規化を行うもので、HTMLではなくサーバーの転送先を指定した.htaccessファイルをアップロードすることで設定します。
canonicalタグと301リダイレクトの違いは、ユーザーに対してページの強制転送をするかしないかです。
301リダイレクトは、検索エンジンやユーザーに対して強制的に指定ページへ移動させるため、下記のような場面で使用します。
- サイトの引っ越し
- サイトのSSL化(http→https)
- 一部のページの引っ越しやディレクトリ変更
- 表示URLを一つにしたいとき(wwwやスラッシュも有無など)
※レンタルサーバーによっては、301リダイレクトが設定できないことがあります。
上記のように301リダイレクトが最適なページには、canonicalタグよりも301リダイレクトを優先させましょう。
canonicalタグを使用するケース
canonicalタグを使用するケースは下記の3つです。
- ABテストを行うとき
- 広告用のLPを作成するとき
- サイズやカラーが違う類似ページが多いとき
canonicalタグの使用頻度が高いのは、サイズやカラーが違う類似ページが多いECサイトでしょう。
ただ、ABテストや広告用LPを利用する企業サイトにも有効です。
canonicalタグを設定する理由

検索エンジンは「canonicalタグ」や「noindexタグ」がページに設定されていなければ、Web上に公開された全ての記事をインデックスします。
インデックスされないようにcanonicalタグを設定する理由は下記の3つです。
- 重複ページをなくすため
- サイトのSEO評価を上げるため
- 被リンク数が正しく評価されるため
順番に解説します。
重複ページをなくすため
下記のように、検索エンジンは同一サイトを別サイトとして認識することがあります。
- 「www.」の有無
- 「http」と「https」
- URLの最後にあるスラッシュ
これら3つの原因でサイトに重複ページがある場合は、正規のURL以外のページにcanonicalタグを設定します。
なぜなら、重複ページが複数あるとSEO評価が下がりページを上位表示できないからです。また、ペナルティを受ける可能性もあるので注意しましょう。
canonicalタグを設定することで、サイトのクロール時間が短くなります。
クロール時間が短くなると新しいページのクロールに多くの時間がかけられ、適正にSEO評価を受けることができます。
サイトのSEO評価を上げるため
重複ページが複数あると、SEO評価は分散してしまいます。
canonicalタグを設定することで、重複ページをなくして、SEO評価を正規のURLに集めることができます。
特にECサイトでは活躍するでしょう。
たとえば、色違いの商品があったとします。同じ商品でも色ごとにページを作成すれば、それは重複ページです。
ただ、canonicalタグを設定して正規のURLを指定することで、サイトの評価を集めることができます。
もっと噛み砕いて解説すると、下記のようになります。
Tシャツのページを1つ作成。(オリジナル商品ページ)
⬇︎
その後、「赤・青・黄」の色違いTシャツを別ページで作成。(計4ページ)
⬇︎
このままでは重複になるので、オリジナル商品ページを正規のURLと指定する
⬇︎
これでSEO評価は分散されず、オリジナル商品ページにSEO評価を集められる
これだけでも、SEO評価はグッと上がりますよ。
被リンク数が正しく評価されるため
類似・重複ページのURLが複数あると、被リンク数が分散して正しい評価が受けられなくなります。
たとえば、「www.」があるページとないページで正規化がされていない場合、被リンクが「www.」ありとなしの両ページに分かれる可能性があります。
被リンク数が分散させないためにも、canonicalタグを設置しましょう。
canonicalタグの設定方法

canonicalタグはhead内に記述するだけなので簡単です。
たとえば、Aページ(正規ページ)とBページ(類似・重複ページ)があるとき、Bページのタグにcanonicalを記述します。
具体的な記述は下記のとおりです。
<link rel=”canonical” href=”正規ページURL”>
設置場所は“重複しているページのタグ内に設置”することを忘れずにしてくださいね。
このようにcanonicalタグを設定することで、BページのアクセスをAページへと移すことができます。
canonicalタグ設定の注意点
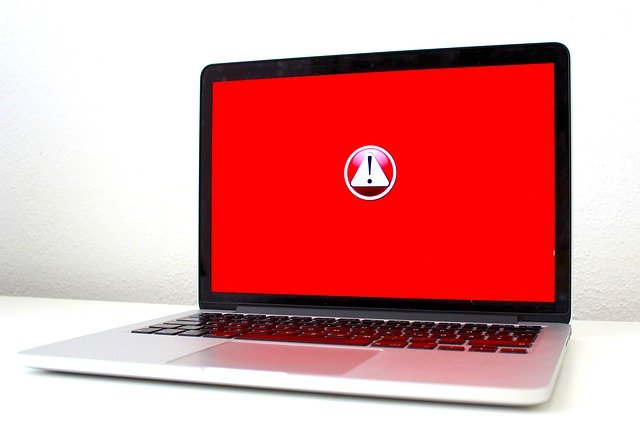
canonicalタグを設定するときの注意点は下記の4つです。
- URLの指定先を間違えて記述していないか確認する
- canonicalページに「noindex」タグがないか確認する
- canonicalページが「エラー」や「404ページ」ではないか確認する
- link rel=”canonical”を1つのページで2つ以上指定していないか確認する
間違って設定すると、サイト全体の流入数が減少する可能性があるので注意しましょう。
canonicalタグ設定後の確認方法

canonicalタグを設定したあとは、下記の手順で正規URLに指定されているか確認しましょう。
- Google Search Consoleにログイン
- 左にある「検索パフォーマンス」をクリック
- スクロールして、グラフ下の「ページ」を選択
- 特定ページのURLをコピー
- コピーしたURLを「URL検査」にペーストする
- URL検査後、ページ中央にある「ガバレッジ」を開く
- インデックス作成欄に「ユーザーが指定した正規URL」と「Googleが選択した正規URL」が一致(Google側は“検査対象のURL”と表示される)していればOK。
canonical設定をしたら、正規のURLと類似・重複ページを確認しましょう。
ただ、canonical設定後すぐに確認しても反映されていないので、2,3日or1週間ほど時間を空けてから確認するといいですよ。
canonicalタグのまとめ

今回は、canonicalタグについて解説しました。
①canonicalタグとは、「ページ(記事)内容が類似・重複している場合、正規のURLがどのページ(記事)内容なのかを検索エンジン(Google)に伝えるタグ」でした。
Ⅰ.類似・重複ページがあると下記のようなリスクがありました。
- SEO評価が分散する
- ペナルティの対象になる
- 被リンク数が正しく評価されない
Ⅱ.301リダイレクトとの違いは、「ユーザーに対してページの強制転送をするかしないか」でした。強制転送するのが301リダイレクト、強制転送しないのがcanonicalです。
また、301リダイレクトは下記のような場面で使用します。
- サイトの引っ越し
- サイトのSSL化(http→https)
- 一部のページの引っ越しやディレクトリ変更
- 表示URLを一つにしたいとき(wwwやスラッシュも有無など)
Ⅲ.canonicalタグを使用するケースは下記の3つでした。
- ABテストを行うとき
- 広告用のLPを作成するとき
- サイズやカラーが違う類似ページが多いとき
②canonicalタグを設定する理由は下記の3つでした。
- 重複ページをなくすため
- サイトのSEO評価を上げるため
- 被リンク数が正しく評価されるため
③canonicalタグの設定方法は、「例.Aページ(正規ページ)とBページ(類似・重複ページ)があった場合、Bページのタグにcanonicalを記述する」でした。
具体的な記述は下記のとおりです。(head内に記述してくださいね)
<link rel=”canonical” href=”正規ページURL”>
Ⅰ.canonicalタグを設定するときは、下記の4点に注意が必要でした。
- URLの指定先を間違えて記述していないか確認する
- canonicalページに「noindex」タグがないか確認する
- canonicalページが「エラー」や「404ページ」ではないか確認する
- link rel=”canonical”を1つのページで2つ以上指定していないか確認する
④canonicalタグ設定後の確認方法は下記の手順でした。
- Google Search Consoleにログイン
- 左にある「検索パフォーマンス」をクリック
- スクロールして、グラフ下の「ページ」を選択
- 特定ページのURLをコピー
- コピーしたURLを「URL検査」にペーストする
- URL検査後、ページ中央にある「ガバレッジ」を開く
- インデックス作成欄に「ユーザーが指定した正規URL」と「Googleが選択した正規URL」が一致(Google側は“検査対象のURL”と表示される)していればOK。
以上です。
canonicalタグは知らない人が多く見過ごされやすいですね。現にぼくも、SEOコンサルをしてはじめて知りましたからね(笑)
canonicalタグの設定は、検索エンジンと検索ユーザーへ有益な情報を届けるために大切な施策のひとつです。
類似・重複ページが見つかれば、必ず対策をしましょう!
これからも良質な情報発信をします。
それでは、次回の記事を楽しみにお待ちください。





